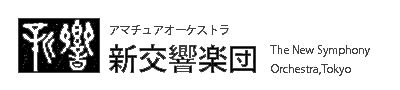大竹 由里子(フルート)
芥川は生涯で100本を超える映画作品の音楽を作曲している。日本の映画産業を音楽面で支えた功績は大きい。
52歳の芥川は、1977(昭和52)年6月に公開された映画「八甲田山」の音楽を担当し、同年10月に公開された映画「八つ墓村」の音楽とともに、1978年第1回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞している。
映画「八甲田山」は、新田次郎の小説『八甲田山 死の彷徨』を原作としており、日露戦争を目前にした1902(明治35)年1月、極寒地での激戦に備え、八甲田山で行われた日本陸軍雪中行軍演習において199名の死亡者を出した「八甲田雪中行軍遭難事件」を題材にしている。厳冬期に弘前と青森から2つの連隊が出発し、八甲田山ですれ違うという雪中行軍は悲劇を生んだ。生死を分けた組織とリーダーのあり方や極限状態での人間模様が描かれた作品であり、神田大尉の「天は我々を見放した…!」と叫んだ名セリフは流行語となり、当時の日本映画界で配給収入の新記録を打ち立てる大ヒットとなった。
第1曲 八甲田山(タイトル)
映画のテーマ音楽であり、悲劇を物語る抒情的なメロディーが心に染み入る。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、オーボエがユニゾンで第1主題を奏で、続いてトランペット、ホルン、クラリネットが第2主題で応え、第1主題に戻る。最後に衛兵ラッパが鳴り、雪中行軍へと向かっていく。
第2曲 徳島隊銀山に向う
徳島大尉(高倉健)率いる弘前第31連隊が、弘前を出発し、十和田湖畔の銀山を目指して雪山を行進していく場面の音楽である。徳島隊は、少数精鋭の27名で、装備を軽くして、十和田湖を迂回する11日間240キロの行程を案内人を立てながら前進していく。小太鼓のリズムに乗って、ホルン、ヴァイオリンが3拍子で勇壮に進むメロディが奏でられる。
第3曲 棺桶の神田大尉
神田大尉(北大路欣也)率いる青森第5連隊は、大隊長の提案で、210名の大規模編成により、3日間の行程で、徳島隊に3日遅れて青森を出発した。行程半ばで天候が悪化、本来指揮権がないはずの随行した大隊長が干渉し、案内人の拒否、物質を運ぶ橇の放棄の反対、夜中の帰営命令、急な方向転換などの結果、猛吹雪の中、遭難することとなった。神田大尉は遭難の責任を取って自決した。徳島大尉は、神田大尉との八甲田で再会する約束が叶うことなく、神田大尉の遺体と対面することとなり、無念さが込み上げる。悲哀に満ちたメロディがヴァイオリンによって奏でられ、深い悲しみの中、静かに終わる。
第4曲 終焉
八甲田雪中行軍の結果、弘前第31連隊は困難を伴いながらも27名全員生還したが、青森第5連隊は210名のうち199名の死者を出した。冬の八甲田山の厳しさとそれに立ち向かう人間を描いた傑作は、壮大なフィナーレで締めくくられる。「芥川節」とも呼ばれる美しく抒情的なメロディは、映像とともに観る人の心に強く訴えかける。芥川の作る映画音楽の真骨頂といえよう。
映像・音楽:
映画「八甲田山」、1977年6月4日公開、森谷司郎監督、橋本プロダクション・東宝映画・シナノ企画
芥川也寸志指揮、東京交響楽団
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、テューバ、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、シンバル、ヴィブラフォン、ハープ、ピアノ、弦五部
参考文献
- 新田次郎「八甲田山 死の彷徨」新潮文庫 1978年
- 出版刊行委員会編「芥川也寸志 その芸術と行動」東京新聞出版局 1990年
- 藤原征生「芥川也寸志とその時代 戦後映画産業と音楽家たち」2025年
- 新・3人の会「日本の作曲家 芥川也寸志」ヤマハミュージックエンターテイメントホールディングス 2023年
- Wikipedia「八甲田山(映画)」(アクセス日:2025年5月13日)