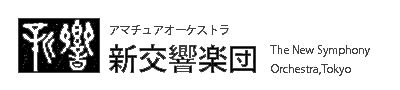本年は新交響楽団の創設者・芥川也寸志の生誕100年であり、これを記念した演奏会シリーズを開催してきました。最後に、芥川先生が1961年の第4回演奏会プログラムへ寄稿した文章を掲載いたします。当時と比較して時代背景も新響も大きく変化していますが、現在の新響にも根付いている想いもあります。
ぼくのアマチュアに関する意見
芥川 也寸志
「ぼくたちはアマチュアですから…」という言葉はよく聞くけれども、その言葉の裏には、さまざまなニュアンスがひそんでいるように思われる。「どうせ下手ですよ」「楽しむことが第一でね」「損得は問題じゃありませんわ」「ぼくたち以外のことなんかどうでもいいや」「プロに似たようなことはいやだね。けがれたくないからね」「……」etc, etc,
勿論、これらの註釈は、たしかにアマチュアリズムの一面を物語るものであろう。〈くろうと〉よりも〈しろうと〉が下手なことは当たり前だし、楽しみのないアマチュアなんてナンセンスに近い。損得を問題にしたらその分だけ楽しみはへろうし、何物にも拘束されない自由な精神こそ、アマチュアのシンボルというべきものだ。また、いたずらにプロの真似をするが如きは、アマたるの厳につつしまねばならぬことに違いない。
しかし、言葉は実に重宝なものである。この「ぼくたちはアマチュアですから…」という言葉が屡々、便法として、いわば一種のいいのがれの手段として用いられているようだ。屡々というよりもむしろ殆どの場合がそうなのではないだろうか?
もしも、この言葉が便法として用いられているのであったら、アマチュアの楽しみは、道楽と全く同じ意味しか持たなくなり、あくまでも個人の生活の範囲を超えることはない。
無論、ぼくはそういう楽しみを否定はしない。道楽としてのコーラス、道楽としてのアンサンブル、道楽としてのオーケストラがあって悪いはずはない。しかし、その楽しみは、決して集団の楽しみとはならないだろう。その楽しみをみんなのものにするためには一つの共通した目的意識を持つことだ。つまりイデエを持つことだが、これは音楽における一つの運動に他ならない。自分の楽しみが同時に他人の楽しみになる――簡単に言えば、運動の楽しみとは、こういう性質のものであろう。
新しい日本の文化的特徴の一つは、一部に優れたものがあってもそれが少しも全体のものになってゆかないという点であろう。それを実証する材料は、いくらでも見つけ出すことが出来る。今、音楽の世界でこれにあてはまる一つの例をひきあいに出せば、日本が生んだ優れた演奏家たちについてだ。
全く異なる音楽伝統の中に、いわゆる西洋音楽を輸入した日本は、長い間の模索時代を経て今や世界にも誇れる、優れた作曲家や演奏家を持つほどにもなった。ベートーヴェンや、モーツアルトが暮らしていた街に生れ、そして彼等と同じ水を飲んで育った音楽家たちとみそ汁や、お茶漬けを食べながらなかば手さぐりで勉強した日本人がコンクールで堂々とわたり合い、しかも立派に彼等を打負かすなどということは、新しい日本の素晴らしさの中でも、一番素晴らしい素晴らしさかもしれない。われわれは、それを心からよろこぶべきだろう。しかし――
こういう優れた演奏家たちは、なかなか日本に帰ってはこない。耳の肥えた聴衆――優れた教師――腕っこきの競争相手――それにもまして本場の雰囲気――それらのものにとりかこまれながら、勉強し、そして演奏活動を続けたいという、彼等の気持ちは無理もない。
しかし、ぼくたちの先輩諸氏による長い間にわたっての努力のおかげで、やっと日本にも、素晴らしい演奏家を持つようになりながら、その素晴らしさが――つまりわれわれの素晴らしさが、少しもわれわれ自身のものにならないとしたら、果して、それを心からよろこんでばかりいられるだろうか。
このような例は、際限なくぼくたちのまわりにころがっている。理由は簡単だ。優れたものと、その反世界ともいうべき末端との差が、あまりにひらきすぎているからである。ヨーロッパが本場なら日本はあまりにも片田舎すぎるのだ。
じゃあどうすればいい?その答えも簡単である。気の長い話かもしれないし、まだるっこい話かもしれないが、とにかく全体が少しずつでも高まる以外に方法はない。そして、そこにこそ音楽運動の本来の意味がある。――
その意味を全うするためには、まず、たとえアマチュアであっても「どうせ下手ですよ…」という意識を捨てなければなるまい。下手でいいのではなく、やはり、断じてうまくなくてはいけない――あるいは、うまくならなくてはいけない――あるいは、うまくなろうとしなくてはいけない。
音楽の価値は、うまいかまずいかではきまらない、というのはぼくの持論でもあり、アマチュア音楽の意義を強調する場合のきまり文句でもあるわけだが、それでも尚、うまいかまずいかは、依然として、音楽の価値をきめる有力な尺度であることは、周知の如く厳たる事実である。
また、楽しむことも必要には違いないが、苦しみを恐れていては運動の壁をつき破ることは極めて困難だ。例えば一つのアンサンブルの中で、技術的に巧拙の差が大きくなりすぎた場合、思想的な対立が起きた場合、外的制約が大きくなった場合、その他に、大きな壁がみんなの前に立ちふさがる。その壁を乗り越えることは、実際生やさしいことではない。しかし、その障害を突破したとき、はじめてアンサンブルのよろこびや楽しみは、運動の実感とともに、みんなのものとなるだろう。
損得はたしかに問題にならぬかもしれぬし、プロの真似をしても何の意味もないかもしれぬ。しかし、アマとプロとを単に経済的概念のみで区別することは、ほとんどナンセンスに近い。スポーツにおけるアマ規定の如きものを、音楽にあてはめたら、およそ音楽運動などというものは成り立たない。もしも、それをアマの純潔と考え、誇りと感じ、節操だと思うのなら、思い違いもはなはだしい。
それどころか活動によって少しでも収益をあげ、それによって個人の生活がなにがしかでもプラスになることが出来れば、それが一番望ましいことだとぼくは考える。たとえ、その収益が、ラーメン一ぱいに満たなくても、それを恥じる必要はない。その収益がささやかなものであったという点においても、また、ささやかながら収益を得たという点においても――。
その形態においては、全くプロと同じでありながら尚、燦然として光り輝いてこそ、アマチュアリズムの名にふさわしいのではないだろうか。このぼくの意見は、屡々大きな誤解をもって迎えられたが、新交響楽団とともに歩いたこの数年間は、ぼくにますますその確信を抱かせた。
今の日本で、アマチュアの果す文化的、音楽的役割は計りしれぬほど大きい。「ぼくたちはアマチュアですから…」が、もっと自然で、もっと明るく、もっと楽しそうに、もっと誇りに満ちた口調で語られることをぼくは期待する。
アマチュアについて、書かねばならないことは、まだまだ多い。これは、そのほんの一部でしかない。しかし、ことによると重要な一部かもしれないのだが――。
1961年4月25日 新交響楽団 第4回演奏会プログラムより