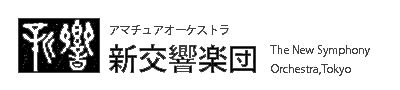髙森 美咲(打楽器)
本演奏会最大のどんちゃん騒ぎが、始まる。
レブエルタスの作風と、映画「マヤ族の夜」
シルベストレ・レブエルタス (Silvestre Revueltas, 1899-1940) は、20世紀前半のメキシコ音楽を代表する作曲家の一人である。
彼の青年期にはメキシコ革命 (1910-1917) が勃発、アメリカやイギリスと経済的な従属を深めていく。独裁政治を押し進めるディアス大統領に対して、農民出身者をリーダーとして反対運動が展開された。そんなメキシコの転換期を生きたレブエルタス。力強い生命力や鮮やかな色彩感、そして時に荒々しくも情熱的な彼の作風に影響を与えたと言っても過言ではないだろう。さらにドビュッシーやストラヴィンスキーといった同時代の作曲家から影響を受けつつ、メキシコの土着的な要素、特に先住民の音楽や民俗音楽のリズムや旋律を組み合わせ、唯一無二の作風を確立させた。
「マヤ族の夜」(La Noche de los Mayas) は、実際のマヤ遺跡で撮影され、1939年に公開された映像作品である。簡単なあらすじは以下の通り。
メキシコ南東部のジャングル奥深くに、現代文明とはほとんど隔絶された、マヤ族の伝統的な生活を送る村があった。そこに迷い込んだのは、白人の探検家であるミゲル。村では狩人のウズが、部族の長の美しい娘ロルに想いを寄せていた。しかし村にやってきたミゲルがロルを誘惑し、村に不吉な影を落とすことになる。
村はその年、水不足に悩まされた。凶作を神の怒りだと考えた村人たちは、ロルに神々の裁きを受けるよう命じ、ロルは生贄にされる運命を宣告されてしまう。それを知ったウズは恋敵であるミゲルを殺め、ミゲルの亡骸をある場所に運ぶ。その場所は、ロルが生贄として捧げられる儀式の場所で…… 愛する人ミゲルの亡骸を見たロルは自ら身を投げ出し、悲劇的に幕を閉じる。
今回演奏する組曲「マヤ族の夜」は、レブエルタスの没後、メキシコの作曲家で指揮者のホセ・イベス・リマントールが1959年に編曲した「リマントール版」である。なんとリマントールは、映画音楽をそのまま抜粋するのではなく打楽器やら特殊楽器やらを「爆盛り」して、組曲として再構成したのである(よくやった!)。リマントール版によって増えた民族楽器たちに、打楽器パートは頭を悩ませる(もとい、ワクワクする)ことになる。
特殊楽器大捜査線
まず、我々打楽器パートがぶち当たった壁は、「楽器そのものが分からない」ということである。さっそく打楽器団員とその知人たちから情報を集め、「多分これだろう」という楽器を集めてくることから始まった。また、全ての民族楽器を揃えることは非常に難しいため、できるだけ民族色の出る素朴な音色を出せるよう、試行錯誤を重ねた。
ここでは、そのごく一部をご紹介する。なお、本番で使用する打楽器については、本プログラムノートの執筆段階では鋭意選定中であり、本番までに変更の可能性があることをお含みおきいただきたい。
ギロ (Guiro)
中南米で演奏される民族楽器。蛇腹の切れ込みが入った木胴をスティックで叩いたりこすったりすることで音を出す。こだわりはバチの部分。ギロ用のバチはないため、菜箸やアイスの棒など、身近にある木製の細い棒をとにかく試した。また、奏法によって多種多様な音色を出せるのが、ギロの面白いところである。どの角度から、どのくらい力を入れて、どれだけ長くバチを当てるか、こだわりの奏法にも注目いただきたい。
ソナハス (Sonajas) または メタルラトル (Metal Rattle)
ソナハスはスペイン語で、”ガラガラ”(ラトル)を表す楽器のことである。ラトルとは、シェイカーやマラカスのように、空洞の容器の中に砂や木の実が入った楽器全般を指す。メタルラトルは言わずもがな、中に金属の粒が入ったラトルである。ラトルは赤ちゃんのおもちゃとして販売されており、もしかしたら、誰もが一度は演奏したことがある楽器なのかもしれない。
そしてこのラトル、シンプルかつ非常に奥が深い楽器である。容器の素材や中身によって、音色に無限の可能性を秘めている。現在は坂入先生と相談しながら、楽器を試作・試奏している。


アルミ缶の中にクリップやコインを詰めており、マラカスのように振って演奏する。
カラコル (Caracol)
巻貝を加工して作られた管楽器である。実は巻貝から作られた楽器は世界中に存在し、地域ごとに生息する貝の種類は違うため、名称や音色はそれぞれ異なっている。日本人が一番イメージしやすいのは法螺貝であろう。
マヤ文明では儀式や祭礼、戦いの合図など、神聖な意味合いを持つ楽器として用いられてきたとされる。ちなみに、マヤ地方の隣にあるアステカ地方には、「法螺貝の人」(テクシステカトル)と呼ばれる月の神がいる。本日は当団ホルン奏者1名とトランペット奏者1名が演奏する。

そんなこんなで、特殊楽器の調達や制作は非常に難航している。ただ、それが打楽器の大きな魅力でもあるのだ。自分たちで好みの音色を楽器から作ることができるのは、打楽器ならではかもしれない。理想の音を見つけ出した時の高揚感は、何物にも代え難い。
彩り豊かな楽章たち
ここからは、組曲「マヤ族の夜」について、楽章ごとに魅力をご紹介する。
第1楽章:マヤ族の夜 (Noche de los Mayas)
モルト・ソステヌート。タムタムと重低音のH、バスドラムの「ドンドン」というリズムに導かれ、荘厳なテーマ曲が奏でられる。深く濃く重々しいメロディに、力強いトロンボーンや雄叫びのようなホルンがアクセントとして加わる。張り詰めた強奏のあと、フルートとヴァイオリンによる情緒的かつ郷愁的な旋律が展開される。続いてバスクラリネットとインディアンドラム(スコアの表記。北米先住民の太鼓一般を指す)、シロフォンがリズムをとり、刹那的で心地よいメロディに移っていく。時折怪しい和音が尾を引きながらも、冒頭のテーマに回帰。物語の始まりに胸が高まるような、期待と力強さを持って締め括られる。
第2楽章:祭りの夜 (Noche de Jaranas)
スケルツォ。1楽章の重厚な雰囲気とは一変し、軽やかで活気に満ちた楽章。
冒頭には「Tempo di Son」と記載されている。Sonとはメキシコやキューバなどのスペイン語圏における民族舞曲を指す言葉のようだ。ギロとソナハスが先導して、終始色彩豊かで爽やかかつリズミカルな音楽が展開される。軽快で心地よい楽章だが、楽譜を見ると5/8拍子や6/8拍子など複雑な拍子がまぜこぜとなっており、奏者泣かせの楽章でもある。最後は祭りの後の静けさを表すように盛り上がりがサッと引いていき、ファゴットとテューバによって句点が打たれる。
第3楽章:ユカタンの夜 (Noche de Yucatán)
アンダンテ・エスプレシーヴォ。「ユカタン」とは、マヤ文明の中心地として知られる半島だ。マヤ族が住んでいた地域は、ほとんど水源がない地域もあれば、熱帯雨林気候の地域や、主力交易品である黒曜石が採れる高地があり、極めて多様な自然環境を有していた。また、マヤ文明は独自の暦(マヤ暦)を持ち、他の文明と比較して天文学が発達していたと考えられる。
第3楽章は他の楽章と一線を画しており、ミゲルがロルに惹かれていくシーンを、一つの音楽として繋げた楽章になっている。弦楽器の深い温かみのある旋律によって、ロルへの切ない恋慕や、波のように心が揺れ動く様子が表現されている。
その後、ソナハスとインディアンドラムに導かれて、フルートが素朴でどこか懐かしいメロディを奏でる。
再び弦楽器の甘美なメロディが戻り、まどろみの中で揺蕩うのも束の間、最終楽章へと切れ目なく移行する。
第4楽章:魔術の夜 (Noche de Encantamiento)
主題と変奏。コントラバスの鞭打つようなピチカートによって、第3楽章のしじまが断ち切られる。クラリネットの不安定なオスティナートとオーボエの怪しいメロディがだんだんと木管楽器や弦楽器に伝播していき、まもなく金管楽器も巻き込み激しい絶叫となる。第4楽章始まって早々クライマックスである。一瞬の静寂の後、4つの変奏曲が展開される。
第1変奏
口火を切るのはボンゴとディープコンガによる8/8拍子のリズム。続いてトムトムが先鋒と同じ8/8拍子で、そこにギロとメタルラトルとトゥムクル(木製打楽器、スコアには高音が異なる2つの低音ウッドブロックで代用可能と記載)が5/8拍子で参戦。さらに大太鼓とインディアンドラム、カラコル(法螺貝)が3/8拍子で応戦。さらにさらに! 4/4拍子で小太鼓(響き線なし)と3連符系のシロフォンとピアノが加勢する。何が何だかわからない! どんちゃん騒ぎの本丸である。大量の打楽器奏者によるポリリズムに呼応するかのように、ホルンが吠え、木管楽器が叫び、弦楽器がオスティナートで煽る。そしてタムタムによる強烈な一打を呼び水に、打楽器奏者の熱狂的カデンツァが始まる。カデンツァは当日のお楽しみ! その後はホルンの咆哮が回帰し、木管楽器の発狂やヴァイオリンの歪みのようなグリッサンドが続いたかと思うと、急激に狂宴が収束する。
第2変奏
第1変奏と同じ順番で打楽器群・カラコル・ピアノが、12/8拍子の異なるポリリズムを引っ提げて会する。トランペットによる影のあるファンファーレに、バンジージャンプのように急激に下降するホルンと取り乱したかのような木管楽器が交錯し、これまた急激に収束する。
第3変奏
4/4拍子。最初からカラコルによる儀式の合図が吹かれる。弦楽器の突き刺すような16分音符に焚き付けられて、トランペットや木管楽器が急激なトランス状態に達するも、またまた急激に収束する。
マヤ族の儀式では、音楽に合わせてアルコールやタバコを摂取し、王様や神官たちがトランス状態になることもあったという。さらに人身供儀の際には、けたたましい叫び声やラッパの恐ろしい響きを捕虜に浴びせながら襲いかかる場面も記録されている。変奏が進むに従い、だんだんと “ハイ” になっていく様子を感じられる。
第4変奏
冒頭から打楽器奏者12名とピアノによる9/8拍子の強奏ポリリズム。本変奏から小太鼓(響き線あり)も加わって、完全にトランス状態だ。強烈かつ屈強な金管楽器やヒステリックな木管楽器、弦楽器群の戦慄したトレモロ。もう誰も止められない。そのまま雪崩れ込むようにフィナーレへと突き進む。
終曲
タムタムの強烈な一打が合図となって、ついに儀式はフィナーレを迎える。第1楽章の荘厳なテーマが打楽器群のポリリズムに加勢する。すでに限界を超えた弦楽器と管楽器をタムタムが追い込み、野性的で荒々しいエネルギーに満ちたまま、壮絶な幕引きを迎える。
「マヤ族の夜」は最初から最後まで気が休まるどころか、色とりどりの展開が次々に繰り広げられ、一つの大きな渦となっていく。
血湧き肉躍る強烈なメロディの数々は、現代に生きる我々が忘れてしまいがちな、自然や生命への感謝を思い出させてくれるように感じる。
皆さまの心に暗い影が落ちるようなことがあった時、この曲が持つ熱い生命力が小さな灯火となってくれたら。そう感じていただけるような演奏を目指したい。
初演(リマントール版):
1960年1月31日、メキシコ・グアダラハラにて、ホセ・イベス・リマントゥール指揮、グアダラハラ交響楽 (Orquestra Sinfónica de Guadalajara)
楽器編成:
フルート2(1番2番ともにピッコロ持ち替え)、オーボエ2、クラリネット2(1番2番ともにEsクラリネット持ち替え)、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン2、テューバ、カラコル(法螺貝)、ティンパニ、ボンゴ、ディープコンガ、トムトム、ギロ、メタルラトル(ソナハス)、トゥムクル、大太鼓、インディアンドラム、小太鼓(響き線なし)、小太鼓(響き線あり)、タムタム、シロフォン、吊りシンバル、ピアノ、弦五部
参考文献
- 譽田亜紀子「知られざるマヤ文明ライフ: え? マヤのピラミッドは真っ赤だったんですか!?」誠文堂新光社 2023年
- IMDb 「Silvestre Revueltas」
- IMDb 「La noche de los Mayas」
- モレリア国際映画祭「La noche de los Mayas」
- Gramophone「REVUELTAS La Noche de los Mayas TRIGOS Concerto No2」
- Wikipedia「シルベストレ・レブエルタス」
- Wikipedia「The Night of the Mayas」
- Try IT「5分でわかる!メキシコ革命の勃発!」
- 東京オペラシティ「メキシコ音楽の祭典 ホセ・アレアン(指揮者)」
- SUZUKI「ギロ」
- ウィキペディア「ラットル(楽器)」(アクセス日:すべて2025年5月20日)