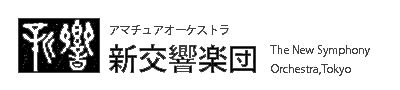大竹 由里子(フルート)
生誕100年記念演奏会のオープニングを飾るのにふさわしい、芥川也寸志代表作の一つである。
1964(昭和39)年、39歳の芥川は、NHK大河ドラマ2作目「赤穂浪士」の音楽を一年間担当し、このテーマ音楽と160曲を超える付随音楽を作曲した。「赤穂浪士」は、 大佛次郎の原作をもとに、赤穂藩の家老 大石内蔵助(長谷川一夫)率いる四十七士が、主君の恨みを晴らすため仇討ちする人間模様が描かれている。NHKは前作がヒットしたことから、歌舞伎役者や映画スターほか豪華キャストの競演でドラマを制作し、芥川の重厚な音楽も話題となり、歴代の大河ドラマの中でも高視聴率を記録した。ドラマの映像は、第7回「松の廊下」一部シーンと第47回「討入り」一話分全体が現存しているのみで、討入りを開始する場面でこのテーマ音楽が勇壮に流れている。
曲は、マーチのテンポの4拍子で、ティンパニと小太鼓(響き線なし)のリズムに乗って、ヴァイオリン・ヴィオラがユニゾンで力強く主旋律をホ短調で演奏する。続いてロ短調に転調し、主旋律はフルート、オーボエ、第2ヴァイオリンに移り、対旋律と絡み合い、8小節ごとに転調しながらフレーズが繰り返されていく。このように、芥川は短いフレーズを繰り返し演奏するオスティナート奏法を作風としていた。フレーズは、新東宝映画「たけくらべ」の自作音楽のモティーフを用いている。また、芥川は映像音楽にチェンバロや鞭を用いたことも特徴として挙げられる。主旋律にチェンバロが加わることで東洋的な響きを生み出し、終始2拍目に鞭の音が打ち込まれることで討入りの厳しさを想起させている。この鞭の音と討入りのイメージが視聴者の共感を得て、レコード制作も行われ、現在でも「忠臣蔵」をイメージする曲となっている。短いフレーズが鞭の音とともに繰り返されるこの曲は、討入りまでの赤穂藩家臣たちの厳しい道のりと本懐に向け一歩ずつ歩を進める四十七士の姿にシンクロし、聴く人々を惹きつけるのではないだろうか。
映像・音楽:
NHK大河ドラマ「赤穂浪士」(放送期間:1964年1月5日 ~ 1964年12月27日、全52回)
芥川也寸志 指揮、コンセール・レニエ
楽器編成:
フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ギター(本日はなし)、ハープ、チェンバロ、ティンパニ、小太鼓(響き線なし)、中太鼓、大太鼓、板むち、弦五部
参考文献
- 出版刊行委員会編「芥川也寸志 その芸術と行動」東京新聞出版局 1990年
- 藤原征生「芥川也寸志とその時代 戦後日本映画産業と音楽家たち」国書刊行会 2025年
- 新・3人の会「日本の作曲家 芥川也寸志」ヤマハミュージックエンターテイメントホールディングス 2023年
- Wikipedia「赤穂浪士(NHK大河ドラマ)」(アクセス日:2025年5月13日)
- NHKオンデマンド「大河ドラマ 赤穂浪士 第47回 討ち入り」(アクセス日:2025年5月13日)