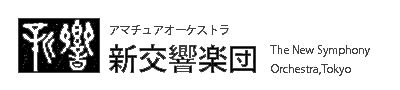伊藤 真理子(ヴァイオリン)
芥川也寸志は、芥川龍之介の三男として1925年に東京で生まれ、戦後日本を代表する作曲家として活躍しました。1954年には国交のなかった当時のソ連へ単身で渡航するという大胆な行動に出ています。携行した自作のスコアとパート譜3曲の中には、1953年に28歳で作曲した「絃楽のための三楽章―トリプティーク」が含まれていました。
1954年、日本では防衛庁と自衛隊が発足し、東宝映画「ゴジラ」が空前のヒットを記録するなど、戦後の社会体制と大衆文化が大きく動き出していました。一方、世界では米ソの冷戦構造が強まり、東西の対立がより顕著になっていた時期でもあります。
いくつかの国の陸路と空路を経てソ連に入国した芥川也寸志は、ショスタコーヴィチ、ハチャトゥリアン、カバレフスキーら当時のソ連を代表する作曲家と交流し、現地で歓迎を受けました。この「絃楽のための三楽章―トリプティーク」はソ連国内で演奏され、芥川也寸志はソ連で当時唯一公式に楽譜が出版された日本人作曲家となりました。
芥川也寸志は作曲活動のみならず指揮者としても精力的に活動しました。1953年以降、隔年で5回実施した「3人の会」(芥川也寸志、團伊玖磨、黛敏郎)のコンサートでは自作の指揮も行いました。そして、終戦の復興期、音楽への強い情熱を抱く市民たちの熱意に深く心を動かされ、1955年にアマチュア音楽家たちの「労音アンサンブル」の指揮を引き受け、さらに翌1956年には、同団体を母体として設立された当団「新交響楽団」の音楽監督に就任しました。
心の底から “音楽が欲しい!アンサンブルが欲しい!” と叫んでいたに違いないのである。(中略)音楽に対するひたむきさ、演奏するよろこびを求める真剣さに出会って、私はいわば契約をむすぶ気になったのである。
(芥川也寸志『ぷれりゅうど』筑摩書店 1990年)
この言葉のとおり、その後生涯にわたって無給の常任指揮者・音楽監督として当団の育成と指導に尽力しました。そして1988年4月24日、旧東京音楽学校奏楽堂で行われた演奏会が、当団との最後の共演となりました。
「音楽はみんなのもの」という芥川也寸志の信念は「代償を求めず、ただひたすらに音楽を愛し、それに没頭していこうという気持ち、それがアマチュア音楽家の中身であり、アマチュア魂というものであろう。」(同上)という言葉によっても表現され、現在も当団の「新交響楽団」の表記の上にはいつも「アマチュアオーケストラ」が小さく添えられています。
さて、「絃楽のための三楽章―トリプティーク」は弦楽五部で作曲された3楽章の編成からなる曲です。NHK交響楽団の常任指揮者であったクルト・ヴェスがニューヨーク・フィルのカーネギー・ホール公演で指揮するために委嘱したものでした。フランス語のTriptyque(トリプティーク)とは3組でひとつになる作品を意味する美術用語です。
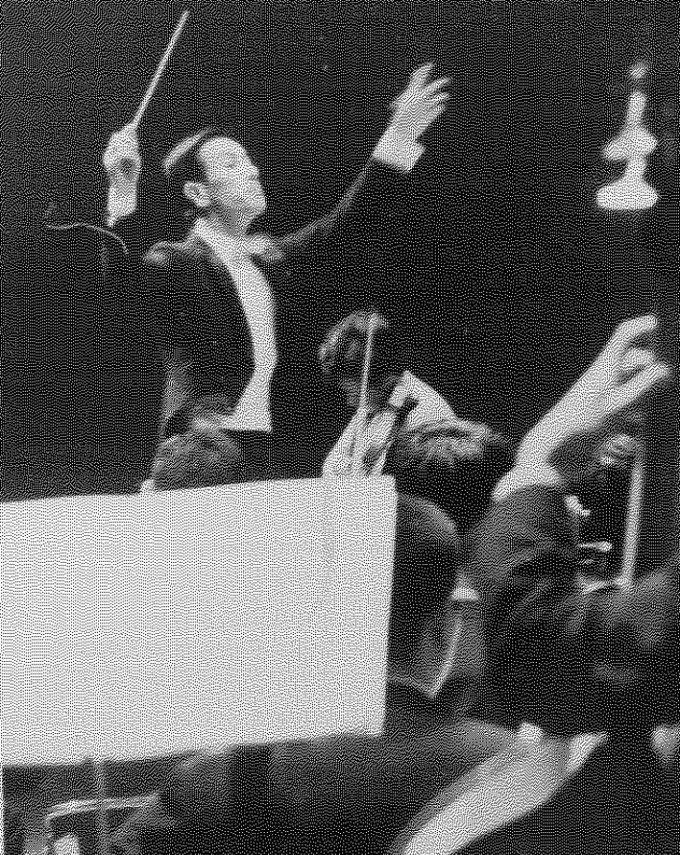
969年10月28日 熊本市民会館(九州沖縄演奏旅行より)
(撮影:田中司、元当団打楽器奏者)
第1楽章 Allegro
楽譜上は4/4拍子のイ短調から始まりますが、それにとらわれない独特のメロディーラインによる全員のユニゾンから始まります。芥川也寸志曰く「リズムなしには音楽は生まれない」(芥川也寸志『音楽の基礎』岩波書店 1971年)という言葉通り、各パートのリズムが押し寄せたあと独奏ヴァイオリンが駆け抜けます。
再び冒頭のメロディーラインが出てくる時、今度はコントラバスが4和音のピツィカートを豪快に弾き、その後の中間部では感傷的なメロディーも出てきますが、短い音型を繰り返すオスティナート技法が全体を支え、一貫した没入感をもたらします。
第2楽章〈子守歌〉Andante
フランス語で「Berceuse」と特記されたこの楽章は、芥川也寸志が自身の娘のために書いた子守歌です。
5/4拍子と提示されていますが、拍子感を意図的に曖昧にしているようにも感じます。ヴィオラによって始まる美しい主題が各パートに受け継がれます。途中で3/4拍子になり、子どもの背中をトントンと優しく叩いてあやすような「Knock the body」という、楽器の木の部分を叩く奏法が始まると牧歌的な雰囲気になり、チェロにメロディーが渡されます。
再び冒頭の拍子に戻り、今度は第2ヴァイオリンとヴィオラが、でんでん太鼓で遊ぶようなリズムを刻み、メロディーや伴奏が各パートに移りながら、夢の中に入っていくかのように ppp(ピアニッシシモ)で静かに終わります。
第3楽章 Presto
2/4、3/8、5/8という変拍子で、密集した和音から始まる主題が次第に各パートの音域に広がっていきます。
リズムに導かれたまま4オクターブまで広がった後、再び冒頭の主題が姿を表します。ヴィオラのメロディーの後、全員の ff(フォルティッシモ)でどこかおどけた調子を呈しながら進み、また冒頭に戻ります。
そこへ突如として、異界に来たかのようなAdagioのメロディーが現れ、目まぐるしい展開の中で主題に戻り、畳みかけるように力強く、息をもつかせぬリズムのユニゾンで締めくくられます。
初演:1953年12月、カーネギー・ホールにて、クルト・ヴェス指揮、ニューヨーク・フィルハーモニック
楽器編成:弦五部
参考文献
- 芥川也寸志『音楽を愛するひとに』筑摩書房 1967年
- 芥川也寸志『音楽の基礎』岩波書店 1971年
- 芥川也寸志『音楽の遊園地』れんが書房 1973年
- 芥川也寸志『ぷれりゅうど』筑摩書房 1990年
- 芥川也寸志『私の音楽談義』筑摩書房 1991年
- 芥川瑠璃子『青春のかたみ 芥川三兄弟』文藝春秋 1993年
- 渡壁煇『楽屋に裏話 人にエピソード』日本実業出版社 1995年
- 新・3人の会『昭和を生き抜いた大作曲家 芥川也寸志』ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 2018年
- 長木誠司(解説)『芥川也寸志/弦楽のための三楽章』(ミニチュア・スコア)音楽之友社 2000年
- ブリタニカ「三連祭壇画」(アクセス日:2025年7月28日)
- ブリタニカ「ゴジラ」(アクセス日:2025年7月28日)