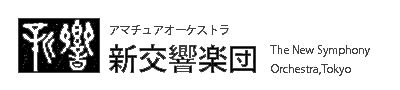M(ヴァイオリン)
■ミャンマーのヤンゴンでの生活②
ヤンゴンでは、チェーンのスーパーマーケット “Marketplace by City Mart”(以下マケプレ)によく買い出しに行きました。食材や日用品が豊富で、外国人向け輸入品も多く、珍しい食材(白きくらげやチャヨテという瓜)や密封の輸入ヨーグルトを巨大な買い物カートに入れて、ワクワク、宝物探しのような気分でお買い物をしました。ミャンマーの『ンガピ』という魚やエビの発酵食品など、食品売り場は様々な香りが飛び交っていました。ビニール袋に詰められて膨らんだご当地の牛乳は、何故か、たまに弾けて床にこぼれていました。

某国の食品用ラップフィルムを買うと(買える事自体が有難いのですが)、独特の香りがして、質感もフワフワで柔らかでした。そのため自宅で上手く切れない事が多く、(日本製品は使いやすく品質が高いのだな、お金を払ってでも欲しいと思う方が多いのではないかな)と改めて感じました。他にも日本の製品の良さを実感する場面は数多くありました。
タイから輸入の冷凍おかめ納豆(3個入りでUS$4程)をお店で見つけた時は嬉しくて、少し偏食気味のわたしの心の拠り所になりました。ある日、納豆をマケプレで見つけてレジに並んでいたら、後ろのミャンマー人女性達がわたしの買い物かごから納豆を取り出して手に取り、楽しそうに笑い喋っていました。納豆の包装に印刷された、おかめの顔が珍しくて面白かったのかもしれません。異邦人であるわたしは、躊躇いがちにニッコリして、そっと目を合わせました。納豆の絵のおかめさんのように。
ところで、日本出国前に維持会マネージャーのM下さんに「東南アジアのお米は炊飯器で炊くのではなくお鍋で茹でると美味しく食べられますよ」と教えて戴きましたので、渡緬後に実践したところ、ミャンマーの細長いお米をちゃんと美味しく茹でることが出来ました。
日本のお米はモッチリしておにぎり(ジビエ肉等を具にしたおにぎりを販売しているお店もありますね)にすることもありますが、ミャンマーのお米はサラサラしてあっさりしていました。


■ミャンマー国内旅行
ミャンマー観光のベストシーズンは、雨がほぼ降らず他の時期に比べて湿度も低く爽やかな、乾季の11月~3月頃です。その気候の時に夫の職場の皆さま・ミャンマー人の職員の方々が家族連れでミャンマー国内旅行に行く機会があり、わたしも何度かご一緒させていただきました。

<チャイティーヨー・パゴダ>
2019年10月にはモン州のチャイティーヨー・パゴダ(仏教寺院のこと)に行きました。標高1,100mのチャイティーヨー山の上に胴回りが25m、高さ6, 7mの、金箔を貼られた巨大な岩が不安定そうに見えながらも転がり落ちずに留まっており、ミャンマー人仏教徒は一生に一度はお参りしたいというほどの神秘的な巡礼地です。
山の麓の町から、荷台を改造して硬い木の椅子を設置した乗り合いトラックが出ていて(トラックには側面や屋根が無い車両もあるそうです)、レールが無いジェットコースターに乗っているような感じで、幅の狭い急勾配の山道を高速、ノンストップで激しく揺れて登ります。
道中がとても険しいらしいと事前に聞いていたので、乗り物酔い止め薬をヤンゴンのスーパーの薬局で買って持参して飲み、わたしにも効きましたが、ご一緒していた日本人の方にもお分けしたところ、薬の効き目がかなり強くて副作用で殆ど気絶のように寝てしまわれました。
その方のチャイティーヨー滞在の記憶を奪ってしまったかもしれず申し訳ない気持ちになりました。
トラックを降りてから徒歩で数十分、パゴダの敷地の入り口で必ず裸足になって入場し、靴は持参した袋に入れてまた入口に戻るまで持ち歩きます。大理石の坂道が続き、わたしの軟弱で平らな足の裏は何度もすべり、そのたびに冷や汗をかきました。目的の岩に着くと男性は売店で金箔を買い、岩に貼ってお祈りする一方、女性は岩から少し離れた場所からお祈りします。
<インレー湖>
翌11月には、シャン州タウンジー県にある標高2,000mの山に囲まれたインレー湖に行きました。
多くのミャンマー人職員の方とご一緒できると聞いて、ミャンマー人が普段からお召しになっている民族衣装(『ロンジー』)をわたしも同じ場で着たいと思い、可愛い花柄や幾何学模様やカラフルな布等で何着か張り切って仕立てて、セットアップで着て行きました。ところが(?)、ミャンマー人の職員の方々は動きやすいジーンズを履かれていました。わたしは(皆さまの普段の本物のロンジー姿を見てみたい)と、勝手に諦めずに全日程でロンジーを着ましたが、やはり皆さまはずっとジーンズスタイルでした。
インレー湖には、片足で船を操る伝統漁業を行い、独自の湖上生活を送る多様な少数民族(首長族もいらっしゃいます)が暮らしていて、観光客は対照的にオレンジ色の救命具を身に着けて剥き出しのエンジンが付いたボートに乗り(操縦は現地の方がしてくれます)伝統的な手作りの蓮で作られた布製品や、銀細工のお土産屋さんやレストランを回ったり、湖上生活している方々の暮らしを身近に感じる事ができます。
エンジンが付いたボートは紐付きの帽子が飛ばされそうな爆速スピードで進んでいくので、「あれ見てください!!」と同乗している方に喋っても、声が「▲〇◇☆×~!?」と、風とすごい騒音で吹き飛ぶので、お互いの感想を共有することはあまり出来ませんでした。





旅行のメンバーで湖上のレストランに集合してお食事していた時、ある日本人メンバーが「水道とか無いようだけど、この料理の食材とかお皿は何処で洗うのかな」と仰ったところ、ミャンマー通の他の日本人メンバーから「知らない方が良い事もあるのよ」と言われていて、世界の深みを垣間見ました。
食後に再びボートに乗り、湖の別の岸に着き、陸上を移動中に道端の屋台で『ロンガン』(龍眼。リュウガンとも呼ばれるライチに似た丸い果物)を山盛り買って食べるミャンマー人メンバーや、それを貰い食べてすぐに体調が悪くなった日本人メンバーの方もいましたが皆でいくつかパコダに参拝しました。

ミャンマーは国民の9割が仏教を信仰している敬虔な仏教国です。ヤンゴンの街中にも出家した僧侶達の托鉢の列をみることがありました。上座部仏教が主流で、現世で功徳を積むことで解脱を目指すというものです。
この功徳を積む事ですが、街の壁の無い食堂で『シャン・カウスエ』というミャンマーの麺料理をいただいている時に、現地の(僧侶ではない)施しを求めるご高齢の女性が近づき、「お金を頂戴」という仕草をされるので、僅かなお金をお渡ししました。その方は何も言わずに静かに背を向け、街の喧騒に紛れるように去っていったので少し驚いていたら、「そのご高齢の女性は、あなたに徳を積ませるために何もお礼を言わなかったのです」というような物事に対する考え方がある事を、後日ミャンマー人の方から聞きました。(そういう考え方もあるのかぁ)と世界の広さを感じました。仏教の他にもキリスト教、イスラム教、ヒンズー教や各種の民間信仰もあり、ヤンゴンの街中に各宗教施設や精霊信仰の巨木がありました。州や民族によって信仰する宗教の割合は異なるようです。




話は変わりますが、2019年に新響の団員KさんとAさんが、それぞれミャンマーにはるばる立ち寄ってくださいました。Aさんとは2019年12月末にエーヤワディー地区にある秘密のリゾート地と言われる(まだ開発の進んでいない)グエサウンビーチに一緒に旅行にいきました。ヤンゴンから自動車で6時間の距離です。地産の大きな海の幸を食べたり、白い砂浜のビーチでベンガル湾の水平線に沈みゆく夕日を眺めながら、軽い飲み心地のミャンマービールを片手に「皆もミャンマーに遊びに来ればいいのにね~☆」とのんびりトークをしました。
半野生の象の背中にAさんと一緒に乗りました。

一方そのころ(2019年末)、インターネットで「中国で新しいウイルスの流行病が発生か」という記事を毎日見かけるようになりました。
■新型コロナウイルスのパンデミック
2020年2月頃、COVID-19(以下、新型コロナ)という言葉がミャンマー国内で定着し、ミャンマー国内の罹患者は徐々に増えてきました。
ミャンマーでもマスクを入手するのが大変で、市場で見つけた際もかなり割高な価格で売られていましたが、皆が競うように大金を払って、某国製のカラフルなマスクを買い求めました。
もし罹患した場合に正直にミャンマー保険省に報告すると、外国人であっても外国人だからという配慮はしてくれなくて、現地の病院(床が地面の野戦病院のような施設)に隔離されることがわかり、病院には看護師も酸素ボンベも足りず自分のことは自分で行わないといけないらしく、ミャンマーのローカル生活に慣れていない外国人の場合は入院したら却って病状が悪化しそうだという話でした。もともとインフラや医療体制が脆弱なこのミャンマーにも、新型コロナが襲ってきたのです。
各国のパンデミック対策により、入国後2週間はホテル隔離されることになりました。もし、ミャンマーで新型コロナで重症化した場合や、その他の病気・大怪我で日本やタイへの緊急搬送が必要となった場合でも、当時は航空便が大幅に減っており、通常の搬送先で受け入れてもらえない可能性がありました。その場合、残念ながら本国への帰還は、無言の帰国となるかもしれないというリスクのある状況でした。
駐在員の奥様とお会いすると「お宅は日本に一時帰国するの?」と話すようになりました。「海外駐在は無事に任期を終えることで6割達成している」と言っていた、どなたかの言葉を思い出しました。ミャンマー国内の感染予防で「夜10時から朝4時まで外出禁止」という夜間外出禁止令が出されるようになりました。
そして、夫の職場から「帯同している家族の強制一時帰国」の指示が出ました。ペットを連れて来ていた方の中には航空会社からのペットの重量制限があったために、制限超過の愛犬を食事制限させて減量させようとしたり、「毛を全部刈ったら体重減るかな」など何とか重量を軽くし一緒に帰ろうと頑張っている方もいました。
■一時帰国
わたしは実家の六畳の部屋に居候させてもらうことになりました。新型コロナが落ち着けば、またミャンマーに再渡航するつもりでいたため、スーツケース2個だけを携えて2020年4月初旬に日本に一時帰国しました。
PCR検査を済ませ、ヤンゴン国際空港で日本行きの飛行機を待つ乗客達は大変な緊張感で(機内でコロナに罹るのではないか)と心配しながら出発ロビーで待機していました。直行便に乗り朝7時の成田空港に到着すると検疫所からの大量の質問書類に記入し、公共交通機関が使用不可のため、空港職員が張り付いて監視している中、予約していたハイヤーで実家の近くのホテルに向かい2週間の自己隔離をしました。
この期間は、わたしはパソコンで絵本を描いたりして過ごしましたが、孤独で誰とも喋らないので、日本語の話し言葉や語彙が咄嗟に出て来なくなりました。ホテルの天井の模様を見つめながら、(自分は何の役にも立たずに空虚な時間が過ぎて、人生とは何だろう)と思ったりしていました。家族やきょうだいの子どもたちの写真や動画を眺め、母に食料を差し入れてもらい、祖母とメールをしながら、隔離明けに家族に会える日を楽しみにして時間を過ごしました。
実家に戻った日、マスクをつけながら両親や祖父母に挨拶すると、彼らはソーシャルディスタンスを保ったまま、とても遠くから「おかえり~♪」と言って手を振ってくれました。コロナ禍でなければ祖父母に抱きつきたかったです。
5月に任天堂Switchをゲットする事ができたのでテレビに繋いで母と一緒に『あつ森』をしました。その時は、ゲームの中で雑草を抜いたり木を揺らして島の生活に夢中になり、久しぶりに、何かに熱中する感覚を思い出しました。
育休中のきょうだいの家に週に何度も遊びにいきました。実家からの23kmを歩いてみたり、きょうだいには会話のリハビリに付き合ってもらいました。きょうだいの子ども達には「伯母さん」ではなくて「Mちゃん」と呼んでもらい、リカちゃん人形で遊んだりヴァイオリンを一緒に弾いたり、プラレールで遊んだり、時には子どもたちを背中の上に乗せて走り回りました。
ミャンマー国内のコロナ禍がいったん落ち着いたということで帯同家族に再び渡航の許可が出たので、2020年12月中旬に再渡緬しました。独りで日本から海外への飛行機に乗る事が初めてで、その飛行機がヤンゴン直行便ではなくクアラルンプールで乗り換えで(空港内の某Sホテルで宿泊)、空港で自力で英語を喋る事にも緊張し、日本で電車に乗るのもよく間違えるので、翌朝、無事に飛行機に乗れた時に「ひとりで外国行きの飛行機乗れたもん♪」と安心してしまい、機内食のビリヤニがとても美味しく感じて、涙を流しながらいただきました。泣いているのが自分で可笑しくなってクスクス笑いました。
わたしの後ろの座席に座った客室乗務員さんは鼻歌を歌っていました。ミャンマーに着く前に別の国に着陸し、一部の乗客の乗り換えがありました。
ミャンマーに入国後、緬政府指定の有料の某Sホテルに隔離されました。食事が毎食充実していたため、持参のSwitchを個室のテレビに接続し、画面のインストラクターとズンバというダンスを踊ってカロリー消費に励みました。1週間後、厳重な感染対策が車内側に施された車で移送され、自宅のアパートへと戻りました。
隔離生活中、久しぶりのヤモリ達を見つけて「あの時のわたしだよ~☆」と話しかけたり、ヴィオラで『浜辺の歌』やお正月の曲を弾いたり、モンゴルのホーミーが歌えるか試して過ごしました。
■国軍クーデター発生
<在住外国人として>
ミャンマーに再渡航して1か月半が経った2021年2月1日のことでした。朝、スマートフォンにインターネットが通じないので(あれ、おかしいな。)と思いました。自宅のテレビをつけるとCNA (Channel News Asia) のニュースで “MYANMAR MILITARY COUP” という赤い文字のテロップと、ヤンゴン市内をミャンマー国軍が包囲した様子が映し出されていました。
その日の明け方前に国内の通信を遮断し、情報統制を始めました。その後、首都ネピドーを含む国内各地で一部の政党関係者や政府関係者を拘束し、その中には必要な心臓病の持病の薬などを十分に持参できない状況で移動を余儀なくされた方もいたと報じられています。国家権力を掌握し国内に非常事態宣言を発出しました。
ネピドーの様子もテレビに映っていましたが、丁度その1年前にわたしもオーケストラの本番に参加し、何気なく眺めたネピドーの片側10車線の道路には、国軍の戦車の隊列が組まれ、ただならぬ緊張感が支配していました。

インターネットが通じず電子メールもLINE等も使えない中、この非常事態は夫の職場からの電話連絡網と、在ミャンマー日本大使館の方が直筆メモをコピーしてくださった紙を、日本人居住者のアパートに一軒づつ配布してださった事により事態を正式に知りました。数日後に、日中の限られた時間帯において通信制限が一時的にでも解除され、その間はインターネットを利用できるようになりました。
2月6日には日本大使館からの領事メール(ミャンマー在住邦人は皆、登録済で受信するメール)で「インスタグラムやツイッター(現X)の利用禁止に係る通達が発出されました」という連絡が来ました。国内で一部の市民が主に夜間に通信手段を使ってFacebookなどのSNSを通じて意見表明や集会の呼びかけを行っていたことに対して、通信の制限が付されました。その後は、VPN(仮想プライベートネットワーク)を利用することで、制限された環境下でも一部の通信が可能となるケースもありました。
在住外国人としてはまずは事態を静観するより他にありません。今後外出できない日が続いた場合に、食料が足り無くなるかもしれないと不安になり、自宅の冷凍庫や保存スペースを確認しました。心配性な性格のおかげで、自宅には缶詰やお米、小麦粉、オートミール等の食料や日用品が思った以上に備蓄されていました。
アパート内のミニマートに、小さな野菜や卵などが売られていたら買って過ごしました。街のスーパー(マケプレ)に出かけたのはその後1か月経ってからでした。お米が無くなった場合に備えて、小麦粉ですいとんのような物や、名もなき食べ物も試しに作ってみたりしました。
<ミャンマー人の動き>
2月1日時点では市民による大きな動きは見られませんでしたが、3日頃から夜8時ごろに鍋を叩いたり、車のクラクションを鳴らすといった、非暴力による意思表示が一部の市民の間で始まりました。
6日以降は、市内で日中にデモや抗議行動が行われるようになり、状況は次第に緊迫し、武力衝突や発砲が発生する場面も見られるようになり、その中で民間人にも犠牲者や負傷者が出たと報じられています。また、民主的な立場を公に示した一部の芸能人や著名人が拘束されたとの情報もあり、拘束後に厳しい取り調べを受けた可能性があるとも伝えられました。
当記事の前編で紹介した国営放送局のオーケストラの複数の楽団員が、演奏を通じて抗議の意思を示す姿がSNSなどで共有されていました。デモの中で負傷された方がいたという話も聞かれます。
放送局が国の機関に属する関係から、民主的な姿勢を持つ一部の楽団員は、政変後に公務員としての立場を辞し自らの意思でオーケストラを離れたとされ、これにより多数のメンバーが退団されたようです。政変前は、楽団員の方たちは食事を共にし、SNS上で “Hey, Bro.” などと日常を分かち合い、気軽なやりとりを楽しんでいた様子が見られました。しかし、情勢の変化により立場の違いから関係性に変化が生じたようです。
なお、かつて放送局でオーケストラの練習中に指揮者の先生が「音楽の仕事で人を(過失で)傷つけることはない」とお話しされたことがあり、その言葉は今も心に残っています。
しかし政変後、将来に希望を抱き職業で音楽活動を行っていた楽団員の一部の方が、民主的な価値観を貫く選択として、楽器ではなく武器を手に取り、ジャングルの奥地に向かったという話も聞きました。
国内でボイコット活動が広範囲に拡大し、公務員に限らず病院や銀行といった公共性の高い機関でも影響が見られました。銀行の職員が出勤を控えることで経済活動に混乱が生じました。また、米ドルなどの外貨引き出しが制限され、ATMには長い行列ができる状況となりました。
地場銀行の業務も長期間にわたり停止し、多くのミャンマー企業で現金不足が発生、従業員への給与支払いに支障が出るケースも報告されました。駐在員で給与を米ドルで受け取っている方々の中には、銀行業務の停止により現金の引き出しが困難となり生活に影響を受けている在住外国人もいました。こうした状況を受けて、外資系企業の撤退が相次ぎ、政府開発援助(ODA)も一部で停止する動きが見られました。
■再び一時帰国
経済活動に混乱が生じる一方で、民主派組織および少数民族武装勢力連合との間で衝突が激化し治安情勢が悪化していきました。報道等によれば、「歩道橋の上に手作りの爆弾が置かれていた」「邦人宅に手榴弾が投げ込まれた」「銃を持ち邦人の自宅に突然訪れて尋問を行った」「治安が悪化し邦人が路上で強盗に遭った」といった事例も伝えられています。また、深夜に自宅周辺で数発の銃声を耳にした事もありました。
夫の勤務先から「帯同家族は治安情勢悪化を鑑み強制的に一時帰国」の指示があり、わたしは持ち込み限度のスーツケース2個と段ボール1個と共に日本へ一時帰国する事となりました。
ミャンマーで得た大切な友であり、わたしの半身でもあったヴィオラも、日本へ連れて帰りたかったのですが、荷物制限のため叶わず、駐在の方に託しました。

ミャンマーでは4月頃、雨季の始まりとともに『パダウ』という木(日本の桜的な存在)が黄色いお花をパッと一瞬で満開に咲かせると聞いていたので、自宅から空港へ向かう道路横に黄色い花が咲いている木が見えた時に、その日に運転をお願いした方(以下、MWZさん)に「あの木は、パダウですよね?」と聞いたところ「いいえ、あれはパダウではなく、良く似ている『ムーワ』という木なんですわ」と教えてくださりました。そういえば駐在の奥様達も「偽パダウがある」と話していたのを思い出しました。
道中で、前を走る軍用車両の荷台の後部に、銃を持ちながら外を監視している兵士が乗っていました。MWZさんは軍用車両が前に見えるたびに、慎重に車間距離を取っていました。
伝聞ですが、ヤンゴン国際空港の入り口で全員X線で荷物を検査されるところで、持参した段ボールに空港職員から目を付けられ開封検査され、ごく普通の健康サプリに難癖をつけて「お金。」とだけ言われUS$100を要求され、お金を渡して解放されて飛行機に乗れた方もいたそうです(当時のミャンマーの都市部の正規雇用層の平均月収はUS$200~600)。
わたしは日本に入国後また2週間隔離生活となり、この時、生活に刺激がもう全く無くなり退屈したわたしを心配したのか、長いこと生活を一緒に噛みしめてきた銀歯が「がちゃり☆彡」と取れて口から脱走し、わたしを驚かせました。
成田空港からハイヤーで移動し実家近くのホテルに泊まりました。優しい叔母が差し入れを沢山送ってくれて隔離生活の静寂を和らげてくれました。父が毎日ホテルの前の道を散歩で通 り過ぎてくれたので、窓から手を振って父の姿が視界から見えなくなるまで様子を眺めました。
隔離終了後、実家の六畳の部屋に再び居候させてもらい、ひとり静かに自分の内面を見つめ続ける事にも飽きた頃、新響のお友達がZoom飲みをしてくれました。パソコン画面越しに懐かしい笑顔が並び、お話ししているうちに、わたしもまた一緒に楽器が弾きたいという気持ちが湧きました。新響の関係者の方に「団友として参加させていただけないでしょうか」とお願い申し上げましたところ、ご配慮いただき有難い事に第256回と第257回に参加させていただきました。(本帰国後、もし新響に再入団させていただけたら、個性豊かで面白い方々ともう一度、ご一緒に音楽を紡ぎたいな)と思ったのでした。
ヤンゴンで暮らしていた頃、かつての日本の幼稚園バスがヤンゴンの市民バスとして第二の人生を送っていました。色あせながらも優しい面影を残したその姿を街で見かけるたびに、わたしはいつもふんわりと励まされたのでした。 ミャンマーでは現在も混乱が続き、深刻に人道支援が必要で政情の安定も見通せぬままです。けれども灼熱の太陽の輝きの下、屋台の果物の香りやスパイスの気配が複雑に入り混じるヤンゴンの街を、あのバスは色鮮やかなロンジーをまとったミャンマー市民を乗せて、今も地道に走り続けているかもしれません。