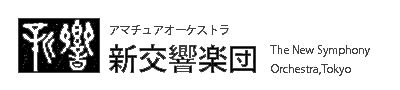小林 優介(ホルン)
今回の映像音楽を取り上げた特別な演奏会のトリを飾る「SF交響ファンタジー」。そのタイトルだけではどんな作品なのかイメージのつかない方も少なくないかもしれないが、冒頭からまもなくして現れる「ドシラ ドシラ……」の節を耳にすれば、きっと合点が行くであろう。1954年に第1作「ゴジラ」が公開されて以来、今なお「シン・ゴジラ」や「ゴジラ‐1.0」といったヒット作を生み出し続ける同シリーズであるが、伊福部昭 (1914-2006) の手になるこのメインテーマは現在も一貫して用いられており、作品のイメージを決定づけるきわめて重要な要素の一つであり続けている。
日本ではまったく前例のない挑戦となったこの「ゴジラ」であるが、かの巨大な怪獣を東京に登場させるには、それだけの裏付けが必要だった。その恰好の材料が、アメリカやソ連が当時繰り返していた水爆実験であり、まさに「ゴジラ」が公開された1954年には第五福竜丸事件によって水爆実験が国民の関心を集めるようになった。驚くべきことに、そうした背景は伊福部が「ゴジラ」の音楽を担当するに際しての原動力ともなった。というのも、第二次世界大戦のさなか夜光塗料の研究に携わっていた次兄・勲が、ラジウムによる放射線障害で命を落としているのである。加えて、伊福部昭本人も林学を大学で修め、戦時中には木製飛行機製作のための強化木材の開発に駆り出されたが、放射線対策の不十分な環境でX線を扱ったことが原因と思われる症状に終戦後も苦しんだ。そのため、「水爆が生んだ現代の恐怖」などと銘打たれたゴジラの存在に対して、放射線と切っても切れない人生を歩んでいた彼が並々ならぬシンパシーを抱いたことは想像に難くない。
さて、この「ゴジラ」の空前の大ヒットを受けて、東宝はいわゆる「怪獣映画」を次々と生み出すこととなり、伊福部も生涯にわたってそれらに携わり続けた。映画そのもののみならず、伊福部によって生み出された数々の音楽に対してもまた、多くのファンが生まれるのは必然であった。
「SF交響ファンタジー」は第1番から第3番まで3曲あるが、これらの3曲は全て1983年8月5日に日比谷公会堂で開催された「伊福部昭・SF特撮映画音楽の夕べ」なる演奏会のために生み出された。もっとも、伊福部自身は「SF交響ファンタジー」の作曲にはあまり乗り気ではなかったようで、あくまでこの日限りの作品であると割り切って編曲を行ったようである。実際、伊福部は「ファンタジー」という言葉を一般的なロマンティックな意味合いを持つ言葉としてではなく、むしろ、「無形式な楽曲」や「各々の楽案が発展・展開していかない曲」といった意味で用いたとのちに語っている。しかしながら、SF交響ファンタジーがその日限りの作品にとどまるはずもなく、中でも「ゴジラ」のテーマに始まるこの第1番が圧倒的な人気を誇っている。
「SF交響ファンタジー」第1番は、低音楽器による重厚なゴジラの動機から幕を開ける。この動機は「ゴジラ」シリーズ全体にたびたび登場するが、本作ではとくに「三大怪獣 地球最大の決戦」におけるアレンジが用いられている。
続いて、あの有名な「ゴジラ」のメインテーマが荘厳に響き渡り、「キングコング対ゴジラ」のタイトルテーマへと滑らかに接続される。そこから「宇宙大戦争」の夜曲へと展開し、音楽は一時、静かで叙情的な表情を見せる。夜曲は、劇中で主人公とヒロインが夜空を見上げる場面に流れる旋律であり、その優しく叙情的な響きは、「戦争」や「破壊」といった物語の主題と対照的な印象を残す。
やがて雰囲気は一変し、「フランケンシュタイン対地底怪獣」における“バラゴンの恐怖”が荒々しく登場する。さらに「三大怪獣 地球最大の決戦」より“ゴジラとラドン”が続き、低音楽器によるゴジラの動機と、トランペットが奏でるラドンの主題が交錯することで、両者の激しい対決が音楽的に描写される。クライマックスに向けては、「宇宙大戦争」のタイトルテーマが姿を現し、「怪獣総進撃」のマーチへと力強く移行する。やがて、「宇宙大戦争」の戦闘シーンを彩る迫力ある音楽が最後を締めくくる。
伊福部は戦後後進の指導にも注力した。東京音楽学校(現在の東京藝術大学)の講師として彼が送り出した数多の弟子の中で、特に重要な一人が芥川也寸志である。芥川もまた生涯にわたって師に対する敬愛を絶やすことはなく、こうした関係が「シンフォニア・タプカーラ」をはじめ新響における伊福部作品演奏の深い歴史と伝統につながっている。もちろん新交響楽団は「SF交響ファンタジー」を何度も演奏しており、そのうちいくつかはCD化もなされているが、意外にも自主演奏会で正規の曲目として取り上げるのは今回が初めてとなる。単なる映画音楽の枠組みを超え、オスティナートの重用や確信に満ちた管弦楽法などといった伊福部作品に一貫する作曲技法の数々を気軽に楽しめるこのSF交響ファンタジー第1番を伊福部らしさ、そして新響らしさ全開の演奏でお届けしたい。
初演:
1983年8月5日、日比谷公会堂にて。汐澤安彦指揮、東京交響楽団
楽器編成:
ピッコロ、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン2、バストロンボーン、テューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓2、吊りシンバル、トムトム2×2人、タムタム、コンガ、ハープ、ピアノ、弦五部
参考文献
- 伊福部昭/広上淳一「宙 – 伊福部昭 SF交響ファンタジー 伊福部昭の芸術4[CD]」キングレコード 1995年
- 片山素秀(片山杜秀)「伊福部昭の肖像」
- 伊福部昭「自作を語る」
- 片山杜秀「伊福部昭 ゴジラへの強い共感」文藝春秋PLUS(アクセス日:2025年5月11日)
- 「教育者、伊福部昭」伊福部昭 公式ホームページ(アクセス日:2025年5月23日)
- 小野俊太郎「ゴジラの精神史」彩流社 2014年