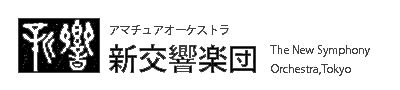坂田 晃一(チェロ)
■ はじめに
これらの4曲はすべて、私、坂田晃一がNHKテレビドラマのテーマ音楽として作曲したものである。当団のプログラム担当委員からの勧めで “解説” を書くことになったが、こうした付随音楽(他の芸術やメディアの表現力を高めるために付随される音楽)は曲自体の音楽的内容の解説よりも、ドラマ本体との関係性やその背景などに重要なポイントがあるので、そうした点について紹介していくことにしたい。
なお、4作とも橋田壽賀子さんによる脚本であるが、おそらく私の音楽が橋田さんに特別に気に入られていたわけではなく、橋田さんの脚本を高く評価していたNHKの一部の制作陣が私の音楽を好んだことや、番組制作のタイミングとの巡り合わせなどの結果である。
■「おしん」
本作は、1983年4月から1984年3月まで放送されたNHK「朝のテレビ小説」第31作のテーマ音楽である。原作・脚本は橋田壽賀子。NHKテレビ放送30周年記念作品として制作され、当時の “朝ドラ” は放送期間を半年間とされていたなかで久々に1年間の放送期間であった。また、1984年11月に記録した、日本のテレビドラマ史上での最高視聴率62.9%という記録は未だに破られていない。
ストーリーは、明治生まれの、貧しい東北の寒村出身の女性が一代にして実業家として成功する話であるが、単なるサクセスストーリーではなく、逆境に耐えながら生きる一人の女性の姿を通して、明治以来の日本女性の生き方を再考するといった企画趣旨のドラマであった。
テーマ音楽は、メランコリックでありながらも憧憬に満ちたメロディをフォルクローレ調の土俗的な力強いリズムに乗せたもので、主人公の、その出自による哀感を秘めつつも数々の艱難辛苦を乗り越えていく前進力を讃えようとした “応援歌” でもある。「これを聴かないと一日が始まらない」といった内容の反響がNHKに数多く寄せられたとのことであった。
オリジナルは小編成のアンサンブルによる演奏であったが、20年ほど前に必要があってオーケストラ用に編曲したものを、さらに今回の演奏会のためにリアレンジを施している。
収録時演奏:新室内楽協会
■「おんな太閤記」
1981年放送のNHK大河ドラマ第19作のテーマ音楽であり、私の大河ドラマ第1作である。主演は佐久間良子。
豊臣秀吉の正室「おねねの方」の目線を通して、秀吉の生きた道を見つめ直そうという、大河ドラマとしては初めての女性路線としての試みであり、橋田壽賀子流の「夫婦論」、「夫論」も随所に見られた。
テーマ音楽は「戦国」と「女性」という、イメージ的に相反するとも言えるものを、ひとつに調和させることを求められたが、女性的な優しさや繊細さの表現にダイナミズムを加えることで、そうした要請に応えている。過酷な戦乱の時代にありながらもその聡明さによって着実に生き抜いた「おねねの方」というひとりの女性像を音楽的に描いているが、彼女の心根の強さは多分に秘められたものであったため、感情やダイナミズムの音楽的表現もやや抑制的にしている。
収録時演奏:小松一彦指揮、NHK交響楽団
■「いのち」
1986年放送の大河ドラマ第24作。主演は三田佳子。
1984年から始まった「近代大河」シリーズの第3作であるが、前2作の視聴率が低迷したため、本作は平均視聴率29.3%と健闘したものの、「近代大河」はこれを最後として僅か3作で姿を消した。
ドラマは、昭和元(1926)年に生まれた女性が、激動の昭和の生き証人として、また、女として、妻として、母として、そして医師として生きる姿を、同じ時代を生きてきた橋田壽賀子が描き上げた。実在の人物が一切登場しないという、大河ドラマとしては異色の作品でもある。
テーマ音楽は、主人公が年老いて自らの人生を振り返るときに感じるであろう“感慨”といったものを描くことを試みた。リリカルに、過ぎ去ったときを慈しむかのような叙情性をもって始まり、多少の起伏ののち最終的に盛り上がるが、ヴァイオリンとピアノという異なる性格の独奏楽器による「二重協奏曲」の装いによって、主人公の多層的な魅力に寄り添おうとしている。
収録時演奏:小松一彦指揮、NHK交響楽団
■「春日局」
1989年放送の大河ドラマ第27作。主演は大原麗子。
ドラマは、春日局像を定説とは異なった、慈愛に溢れ、家光をこよなく愛する女性として描いている。
音楽は、ドラマ全般に日本的な響きや旋法に依らずに、西洋音楽の中世的な旋法(ギリシャ旋法)に類するものや、機能和声的ではない転調を多用することによって、時代劇として特徴ある音楽世界を創りあげた。テーマ曲でも同様の手法に加え、オーケストラの1パートして女性コーラスをノン・ヴィブラートのブルガリアン・ヴォイス風に仕立てることで、主人公が時折みせる厳しさを象徴的に表していたが、本演奏会では諸般の事情によりコーラスを設えることはできないので、コーラスパートをオーケストラ内の楽器に埋め込むかたちへ、オーケストレーションに多少の改変を加えている。
収録時演奏:高関 健指揮、NHK交響楽団
■おわりに
私は作曲を業とする、プロフェショナルの音楽家であるが、同時に当「アマチュアオーケストラ 新交響楽団」のチェロのメンバーでもある。私の友人のなかには、私がアマチュアの団体に籍を置くことに違和感を唱えるものもいる。しかし私は、音楽を純粋に楽しむためにはアマチュアであることが絶対条件であると、遙か昔に職業音楽家として歩み始めてすぐに気付いてしまったのである。その気付きから50数年後、私は “アマチュア” として音楽を純粋に楽しもうと決意し、当団の入団オーディションを受けた。チェロには、作曲家になろうと決意してから30年近くは全く触れない期間もあったので、技術的にはなかなか覚束ないものもあったが、なんとか入団することができた。
入団後9年が経ち、一団員として “音楽を純粋に” 楽しんで来ていたのであるが、今回の演奏会の企画趣旨に私の作品が適合していたためプログラムに加えられることになった。そして、作曲者自身がオーケストラの一員として演奏に加わるという不思議でもあり、楽しくもあるという、大変レアな経験をすることになったのである。
< 坂田晃一 プロフィール >

1942年、東京生まれ。演奏家を目指して東京芸術大学器楽科に入学するが、作曲家への進路変更のため中退。作曲・指揮を山本直純に師事し、アシスタントを務めながら商業音楽作曲のあらゆるジャンルについて徹底的な訓練を受ける。1965年よりテレビドラマ、映画、レコード、舞台、CM等、幅広い作曲活動を展開、主な作品にNHK「朝ドラ」「大河ドラマ」他、NTV「池中玄太80キロ」他、テレビ朝日「家政婦は見た」他、アニメ「母をたずねて三千里」、ジブリ「コクリコ坂から」主題歌、西田敏行「もしもピアノが弾けたなら」、杉田かおる「鳥の詩」、ビリーバンバン「さよならをするために」等がある。